

『 余った壁紙を ○○さんから貰ったんだけど、栗山さんどうかなあ。 トイレの壁紙張替えてもらえんかなあ。』
『 え~、無理でしょう。 やった事ないですよ。 』
『 そうか・・。 栗山さんがヤッテくれないとなると、私らが二人でやらんと しょうがないなあ・・。 』
『 ・・・わかりました。 お二人より 私が出来ると思います。 』 『 そう? ありがとう! 』
というわけで、とある画廊のトイレで作業してきました。
障子・襖の張替え依頼は受けた事がありましたが、壁紙は初めてです。 ネット動画でも勉強しました。 掛け軸表装とは道具も違います。
掛け軸表装とは道具も違います。
緊張感高まります。 自分の家の張替えさえやった事がないのに、自分の家とは違いますから・・。
 作業前。 そうですねえ、年が経つと継ぎ目から痛んできます。 午前11時・剥がし作業開始。
作業前。 そうですねえ、年が経つと継ぎ目から痛んできます。 午前11時・剥がし作業開始。
下地を調節し、新しいクロスに糊を引いて ヨイショと持ち上げる・・糊がビッシリ引かれた2・5mのクロス、この運び方は動画さまさまでした。
余った壁紙利用なので3種類を張り継ぎます。 どうなるかと思っていましたが、なかなか御洒落なトイレとなりました。

 終わりました・・・。 午後5時すぎ・。
終わりました・・・。 午後5時すぎ・。
密室内での慣れない作業、ここしばらくでかいた事無い程の汗をかきました。 黒いポロシャツに塩ラインが現れるほど・・。 精一杯やりましたが、先々どうでしょう?
その道その道のプロに頭を下げます。 勉強になりました。
この画廊を訪れる時、しばらくは 接着剤を持参して トイレを覗かなくてはなりません。 (笑)
古い書軸の修復を依頼される時、同時に頼まれる事があります。
『 何と書いてあるのか? 誰が書いたものなのか? 調べて教えてください。 』
・・・簡単に言われますけど、私 いたって浅学の身にて、困る事が多いのです。 そういう時、頼りになる師匠のところに走ります。![002[3]](http://sairenji.jp/SR/wp-content/uploads/2012/06/0023-225x300.jpg) これなんかも、何という方のお名前か・・・・?・・・さっぱり。
これなんかも、何という方のお名前か・・・・?・・・さっぱり。
師匠は丁寧に、< 書体・くずし字辞典 > を広げて 『 ほら、この字は ここに出ている。 』 と、さし示しながら
時間をかけて教えて下さいます。 ただ読むだけでなく、そこから 色んな事に話題を広げてお話して下さいます。 ちなみにこれは ≪ 韓 玉林 ≫書 。 ( 書、は 解るんですよ。 さすがに。 一緒に読もうとして下さるので、くずされた字も 少しずつは読めるようには・・・いや、また 偉そう病が。 人によく見られたい病が。 お恥ずかしい。 )![003[3]](http://sairenji.jp/SR/wp-content/uploads/2012/06/0033-225x300.jpg) ≪ 臣玉林印≫ と ≪ 昌黎韓氏 ≫。 100年位前のお方。
≪ 臣玉林印≫ と ≪ 昌黎韓氏 ≫。 100年位前のお方。![001[3]](http://sairenji.jp/SR/wp-content/uploads/2012/06/0013-225x300.jpg) ≪ 士不可以不弘毅 ≫ であるとの事。
≪ 士不可以不弘毅 ≫ であるとの事。
師匠、またまた何処からか 分厚い本を持ってきて 『 ほら、ここにある。 中国宋代の儒学者・朱熹の言葉やな。 』 『 して その心は? 』
『 もののふは、全てが 度量・意志が強いというわけではない・・・・っちゅう事かな。 』
師匠、くれぐれもご自愛頂き・・・長生きして下さい! また、困った顔してやって来ます!
 ≪ みやこメッセ ≫ にて。
≪ みやこメッセ ≫ にて。
数十ヶ廊の画廊・古美術廊がブースを設けて集いました。
普段は付けておられない値札を置いての展示でした。 わたしでさえ知っている方々の名のついた作品が、ジックリ見てまわるには苦しいくらいに・・・・・。 ( 名はどうあれ、ほう・・と思って下の札を見ると おお・・とビックリする名と値札が・・。 という事です。 )
其処らへんはソコソコに、今日の目的・なにより行きたかった ≪ 京都芸大ブース ≫ へ。
今までだったら ( こういう ) 会には参加されないであろう所が 参加されたんですから・・。 ( かな?)
日本画 ( ・・この言葉の持つ難しさは 井上君から勉強中ですが。 ) の先生方の作品が並びます。
その中に正ちゃんの≪ 地蔵菩薩・模写 ≫ ( 正垣雅子先生・和服でバツっと決めてましたね。 カッコよかったですよ! )、栗山が額装したのがありました。 二人で苦労したんです、インド古裂をアシラッテ。 ねえ・・・。 悩んだ時間だけ 良い モノになりましたねえ。 好評だったとの事、実に嬉しいかぎりです。
それもともかく。
川嶋渉先生指導の < 日本画体験 > イベントの見学もできました。



実に楽しそうな参加者のお顔が印象に残りました。 ・・栗山も また 描いてみたくなる様な・・。
海の向こうで画を教えておられるというお方・・、どうですか?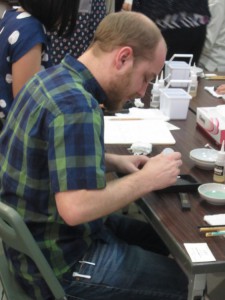
先生の< 画材コレクション >も。

 宝石をゴリゴリ磨るところからされていましたが、<緑>の色を出すにも、こんなに種類が分かれていて、これをまた 組み合わせると無限に広がるんですねえ・・色の世界は。
宝石をゴリゴリ磨るところからされていましたが、<緑>の色を出すにも、こんなに種類が分かれていて、これをまた 組み合わせると無限に広がるんですねえ・・色の世界は。
< 見る > 楽しみが増えました。 ・・などと偉そうに。
合い間に、以前から少々お知り合いの先生ともお話しながら、会場の知人とご挨拶を交わしながら。
沢山の人の中で、笑顔で 「 おひさしぶりです! 」 って言い合える事の嬉しさを実感した日でもありました。
< 挨拶 >って人を元気にしますね!




