

5月1日。
今年も白藤、見事に見せてくれました。

やがてこぼれ散る花ですが、空しい事ではありません。
「 帰るべき 地あらば零れ 藤の花 」
「 散ることは 地に還る事 藤の花 」
弥栄・勝龍寺前住職 故 紀令持師、この藤を見て詠みし
平成3年5月
しばらくご挨拶いたしておりませんでした。今日はすでに4月19日。
未だ新型ウイルス禍おさまり見えぬ中ではありますが、3月21日には彼岸法座、4月8日には永代経法要を開座いたしました。 マスク・消毒・換気・黙食。
マスク・消毒・換気・黙食。 肌寒い山里では、梅と桜とレンギョウが揃って。
肌寒い山里では、梅と桜とレンギョウが揃って。
お彼岸と永代経ではお斎お昼食の姿はかなり違います。
 永代経は塗のお椀にて。当寺にては年7回の法座のうちで永代経と報恩講の2回に塗のお椀が登場いたします。
永代経は塗のお椀にて。当寺にては年7回の法座のうちで永代経と報恩講の2回に塗のお椀が登場いたします。
早朝よりの台所お世話方の皆さまへの感謝、毎回深々と。



お勤め聴聞第一ではありますが、お昼に皆さまと同じ場で同じものを頂く事、有難いことでございます。今は黙食せざるを得ませんが、早く以前のように楽しく会話しながらの時間を頂きたいものです。
永代経法要のご講師には広島市の永光寺・永光聖法師に4年ぶりに出講頂きました。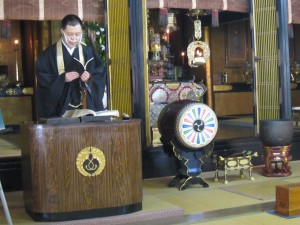
お人柄溢れる穏やかなお話しぶりに時間短く感じました。  「大丈夫」のお話がこころに残ります。お話しを聴かせて頂きながら私の中の様々なものが出て来て、想い巡らす貴重な時間を頂戴いたしました。(『わたしは大丈夫だ』というひとほど危ないですね)
「大丈夫」のお話がこころに残ります。お話しを聴かせて頂きながら私の中の様々なものが出て来て、想い巡らす貴重な時間を頂戴いたしました。(『わたしは大丈夫だ』というひとほど危ないですね) 

4月8日、境内の白藤の様子をうかがうとまだまだ何事もなく老木の姿で立ち尽くしているばかり。 どうでしょう、はたして今年も白い房を見せてくれるでしょうか。




1月16日、当山御正忌法座。

新型ウイルスおさまらぬ中でありますが、お参りの方有る無しにかかわらず親鸞聖人祥月ご命日に合わせたお勤めは、例年通り午前午後と。歩いては遠い所からのお方ばかりにて、温かい「けんちん汁」を用意して頂きます。  この世情でありますからお食事は遠慮されてのお方もありますが、換気良い広い所でマスク付け外ししながらお喋りは無しで。
この世情でありますからお食事は遠慮されてのお方もありますが、換気良い広い所でマスク付け外ししながらお喋りは無しで。
報恩講のお椀と違って小皿物が並ぶのも華やいで綺麗です。 


お勤めの間間に住職の法話を。一日で40分のお話しを4回です、お顔もお名前も知ったお方々ばかり、ゆったりとした仏法聴聞の時間をご一緒させて頂きました。
「渋柿」「不断煩悩得涅槃」「雪の道」
この度出来上がり持ち帰ったチラシ。わたしの『1分間法話』ひとこと話のチラシもご紹介。
会う人限られた世界でありますが、今の時代は電子メールで、お会いした事の無い方にもお便りを届けられる時代。 厳密に「法話」と言えないにしても、お坊さんからたまに1分で読める「お便り」が届くと思っていただければと。 それがホッとひと息をつける時間になればと。 それがひょっとしたら聴聞へのなんらかのご縁になればと。
息子に提案されて、さてどういう形で出来るか共に試行錯誤。 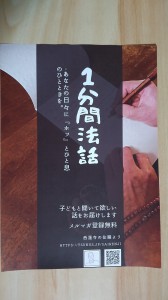
15分法話として動画で撮ったものもありますし、1分間法話として動画を撮ったものもありますが、今のところメールアドレス登録頂いたお方に「お便りを書いてお届けする」というのがわたしにはシックリ。
一年半の間に15通ばかりを書き届けましたが、次第にこの「メールマガジン」読んで下さるお方が増えてきております。どなたが読んで下さっているかはこちらには分からない様になっていますが、その時発送する数だけは分かる様になっておりますもので。 どうやらお寺まいりのご縁なき若いお方が多いようです ( 知らんけど ((笑)) ) うれしいことです。
「QRコード入れたチラシ作ったらどう。 自分が出会うひとに紹介するにもそれがあった方がずっといい。」
と言われ、成程と。 どんなのが良いか任せるから作ってくれと。
じゃ、先ず住職が手紙を書いてる写真を撮ろう。 それを表にして、裏に「1分間法話」のどれかを入れ込もう。 ・・・と提案され話は進み、デザインは彼が友人(彼女?)に依頼しアッとという間に届けられました。 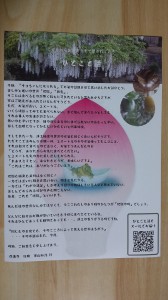 早いですね、若いっていうのか性格なのか、あ~しようかなどうかな・・出来るかな~・・した方がいいのかな~てオジサンとは違います。
早いですね、若いっていうのか性格なのか、あ~しようかなどうかな・・出来るかな~・・した方がいいのかな~てオジサンとは違います。
立派な良いのが出来ました! これまた嬉しいもんです、形になると。
「 出来る事を 出来る時に 出来るかぎり 出来るところまで 」させてもらってゆきましょう。
https://home.tsuku2.jp/storeDetail.php?scd=0000113512
このページのずっと下のほうに、『メールマガジンバックナンバー』とあります。
そこで今まで配信した「お便り」がすべてお読みいただけます。




