

 湖東三山の一寺・金剛輪寺 ( 滋賀県・愛荘町 )。
湖東三山の一寺・金剛輪寺 ( 滋賀県・愛荘町 )。
あるお方のおともをして行って参りました。天平13年 (741) に行基上人が開かれた古刹です。 広い敷地の中を歩きます。 包む小雨、土の香り 苔の香り 石の香り・・・。 紅葉の時期は さぞかし美しい事だろうとも想いながら・・。 天台宗の宗務総長を務められた濱中光礼住職とお会いし色々なお話をお聞かせ頂きました。 とある大きな事が決まる瞬間に末席で立ち合わせていただきました。 ああ・・こういう事を大事にお考えであるのか。 なるほど・・ と 。
天台宗の宗務総長を務められた濱中光礼住職とお会いし色々なお話をお聞かせ頂きました。 とある大きな事が決まる瞬間に末席で立ち合わせていただきました。 ああ・・こういう事を大事にお考えであるのか。 なるほど・・ と 。
しばらくして 『 え~と、あなたは表具屋さん? うちには出入りのところが幾つもあるからなあ・・。 』
それはそうでしょう、数年前 800年前の曼荼羅を大修復された事はニュースにもなりました。
わたしも仕事をいただきたくてやって来たわけではありません。
『 存じ上げております。 滋賀には腕のいい表具屋、表具師が沢山おられる事も存じております。 』 ・・正直なところです。
帰り際、『 これを 軸にしてみてくれるか? 』 と頂かれていた <絵手紙>
を手渡されました。 『 表具をするひとは何人もいるんだがね・・。 』 と笑いながら。
ありがとうございます。 今日のご縁、楽しみながら表装させて頂きます。 栗山が預かったかぎりは
『 ほう・・。 』 と言われるものに仕上げてお見せします。
とある方からご質問がありました。 < 南無阿弥陀佛 >の名号の下に描かれている < 蓮台 >に色・形等、決まり事がありますか? ・・・と。
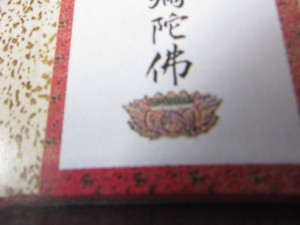

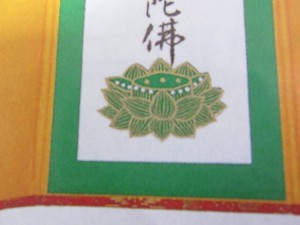
 墨のみで描かれたもの、彩色が施されたもの・・様々です。 どう描くのが正しい、という事はないと思います。 どの色を使ってはいけない、という事もないと思います。
墨のみで描かれたもの、彩色が施されたもの・・様々です。 どう描くのが正しい、という事はないと思います。 どの色を使ってはいけない、という事もないと思います。
こんなのにも出会いました。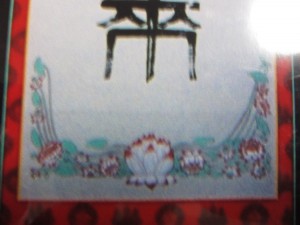 中国・敦煌の画家< 馬強 >氏が描いたものです。 敦煌・莫高窟の壁面のどこかにあるとか・・・。
中国・敦煌の画家< 馬強 >氏が描いたものです。 敦煌・莫高窟の壁面のどこかにあるとか・・・。
泥中に根を張り その水と養分を吸いこみながらも、決して泥の色には咲かず自らの色で大輪を咲かす < 蓮 >。 いや、泥中からこそ咲く < 蓮 >。
五濁 ( 劫濁・見濁・煩悩濁・衆生濁・命濁 ) と説かれる濁った世でも、世でこそ はたらく < 法 >。
自己中心の煩悩にまみれている私の中にこそ はたらく教え。
仏教では蓮の華を < 法 >の象徴として大事に描かれてきました。 絵像の仏さまも 蓮の中に立たれておられます。 どう描かなくてはならない、という決まり事はないと思います。 ・・・ 『 いや、そんな事はない。 』 と仰るお方は、どうぞご教授下さい。
どう描かなくてはならない、という決まり事はないと思います。 ・・・ 『 いや、そんな事はない。 』 と仰るお方は、どうぞご教授下さい。
もうひとつ、名号の文字についてもご質問がありました。
< 南無阿弥陀佛 > も < 南旡阿弥陀佛 > も < 南無阿弥陀仏 > も、文字の違いはあっても同じこころを伝えられてあります。 もっといえば < 帰命尽十方無碍光如来 > も < 南無不可思議光如来 > も同じく阿弥陀如来をあらわす 名号です。 ・・・・分りにくくなってきましたか?
今度 ゆっくりお話しましょうね。





