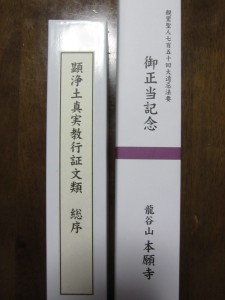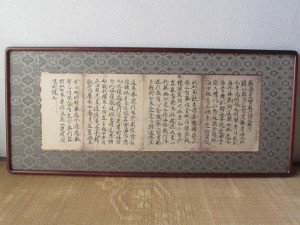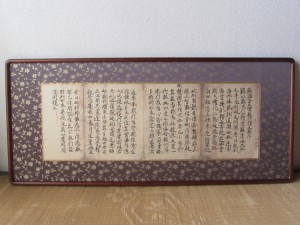先代、先先代が ( その前の方々の姿は見ていないので 分りません ) 清楚な生活をしていても、< 香 > は良いモノを使っていたと書きましたが、それには山陰・石見地方の伝統風習が色濃く影響していると思われます。
石見地方の法事。 読経勤行とご法話の間、回し焼香 ( 焼香の為、香炉と香葢をのせた御盆を 施主から順番に参詣の方全員に回す ) の時、10円・・100円と硬貨を御盆にのせてから香をつままれています。
通夜・葬儀の焼香の時も、前に進み出て香を火種に乗せる前に 10円・・100円の硬貨を机の上に置いておられます。 なぜ置かれるのか? おそらく・・・。
自分では香を持参していないので、この備え付けの香を使わせて頂きます・・ついては、この香への代金?として置いてまいります。 ということから始まったのではないかと思います。
京都・大阪 ( 他の地方はよく知りません ) では無い習慣です。 誰も硬貨を置いていかれません。 置いていかれる地方の風習はとても丁寧な事だと思います。 < MAY 香 > を持っていかれていると硬貨を置く必要はなくなりますがね・・。
という事で、< 香 > の為に納められた浄財なので、貯めておいて < 香 > を求める。 他の事に使わない。
そして、少々高価でも < 良い香 > を皆さんに焚いてもらう。 法を聞く場を整えて頂く。
・・・・そういう事だったんだろうと思います。
西蓮寺のみならず どこの寺院もそうであろうと思います。 聞いていないので分りませんが・・。
方々の姿勢を敬っている事に変わりはありません。
今日のお参りで話題になりました。 『 なぜ、仏事では焼香するんですか? 』
香を焚く・・。わたしが聞き学んだところですが。
お釈迦さまがお話をされる時、沢山の方が集まられます。 2500年前のインド、水の貴重な暑い国にて一か所に多くのひとが集まると人間の臭いはかなりのもの・・・。 せっかくのお話もその臭いが気になって心静かに聞く事が難しい。 そこで、ゆっくり聴聞できる様にと良い香りのする < 香木 > が焚かれはじめた・・と。
< 香を焚く > という事は、仏事の場を整える・荘厳する事。 読経勤行をご一緒し その後のご法話を心落ち着けて聞かせて頂く < 場所 >作りに、わたしも一助携わらせて頂きます・・と、香を一つまみ。 ・・・そう聞き学んでおります。
香には色々ありますね。 形では、線香・抹香・塗香・・素材では、伽羅・沈香・白檀・・。
大変安いものから ( 杉の木に匂いをしみ込ませて粉にしたり )、 とても高価なもの ( 日本には無い香木を刻んであったり )まで。
『 線香臭~い。 』 と言われるような煙だけはモクモク出ても 咽て頭が痛くなる様なものでなく、良い香り・好きな香りの香を焚きたいものです。 ・・少々高価でも。 ほんの少しでも香りの広がりが違います。
決して贅沢なことではないように思うのですが。
ちょっと美味しいものを我慢して、いい香を・・ダメですかねえ。
先代も先先代もそうでしたから、私もそうしています。 ≪ MAY 香 ≫ 。
焼香する時は、備え付けの香でなく自分が持参した香を袂から出して一つまみ・・・合掌 礼拝。
法事の回し焼香には、持参した自分の香葢を回し皆さんに焼香して頂く。
決して裕福ではなく、穴の開いたモノを繕って身につけてましたし 根っこと葉っぱばかり食べていましたが、
< 香 >はいいモノを使っていました。
仏さま、亡き方、仏法を敬っていたのだと思います。 ・・・その方々を尊敬しております。