

文章を書く事が多い方とは 知っていました。
お話をしていて流れから何気なく出された < 原稿用紙 > ・・・・・・『 ん~~? 』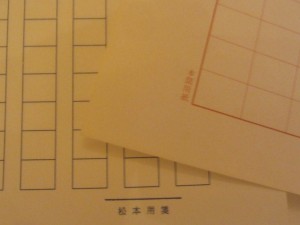 端っこに < 本間用紙 > と入っています。
端っこに < 本間用紙 > と入っています。
『 これ、本間さんのオリジナル原稿用紙ですか? 』 『 そう。 横に広い角が書きやすいから。 』
・・・・へ~~。 かっこいい~! なんて言っていたら、横におられた御人、『 俺のも あるで。 』
えっ ・・・『 出た~。 』 松本さんの < 松本用箋> 。
絶対、万年筆ですよね。 インクにもこだわりの色がありますよね。
・・・・・・何を あたり前の事を・・と言いたげな眼差し。
いつか 作りたいですね、 < 栗山用箋 > 。 しょうもない事なんか書けなくなりそうですが・・。
島根県は < 出雲 >の国と < 石見 >の国に分かれていました。
浜田・三隅は < 石見 >の国、石州です。 ここで漉かれてきた紙を < 石州和紙 > といいます。
人口7000人弱の三隅町に6軒の和紙工房・製作所があります。
2010年にユネスコ文化遺産に認定された < 石州和紙 >。 先日訪れた 和紙会館に今日も立ち寄りました。
『 ブータンの紙もありましたよ。 』 と書いたところ、和歌山の書家・清水先生から問い合わせとご依頼がありました。 ・・・・『 5月にする個展で 100枚の種類の違う紙に< 愛 >と書いて並べたいと思い、色紙・和紙を集めてます。 是非、そこで色んな紙を入手してきて下さい。 』 ブータンの紙。 ツァショー・ダフネという材料から作られたかなり厚みのあるザックリとした紙。
ブータンの紙。 ツァショー・ダフネという材料から作られたかなり厚みのあるザックリとした紙。
 裏と表が剥がせそうなほどです。
裏と表が剥がせそうなほどです。
< トロロアオイ >を使用する和紙漉き技術を学んでから、日本の様な薄くても丈夫な紙を生産できる様になっておられるそうです。 喜ばしいことです。
以前のゴツゴツした紙の伝統も伝えて頂きたいと思いつつ、一路京都を目指します。





